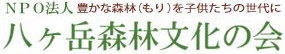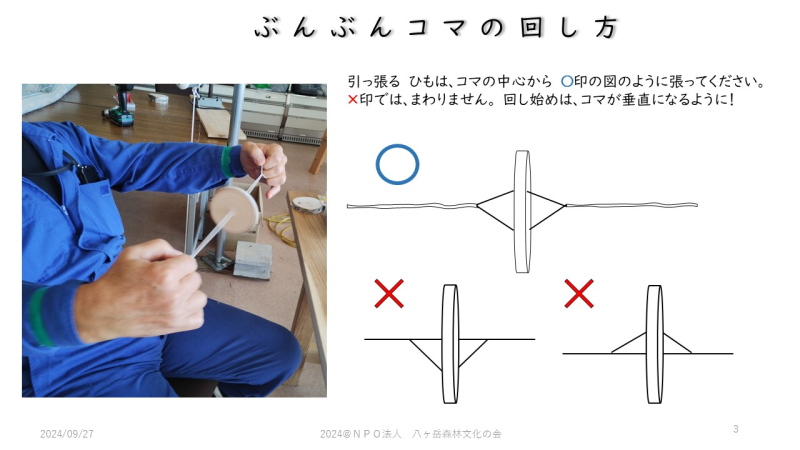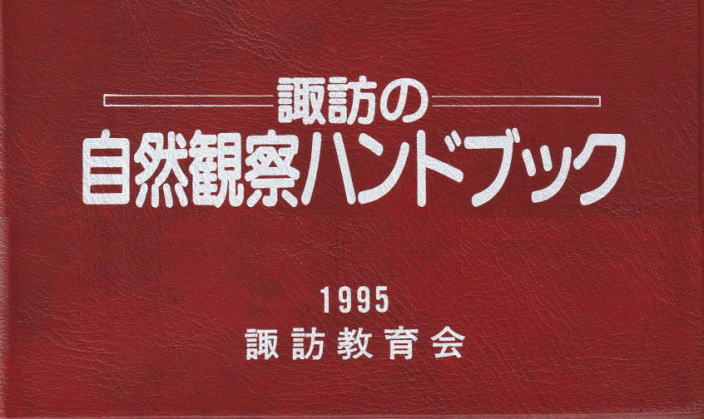活動内容: 森林に学ぶ
11月4日 市民の森 秋の観察会 参加者募集
落葉して樹皮が目立つようになる時期に地衣類に焦点をあて、講師を升本宙(ひろし)氏(信州大学農学部助教)「『地衣類』という生き物」について、講義とフィールド観察により理解を深めます。
森林文化学習会 9月
今年度の教本は、諏訪地域の自然を確認しようと、諏訪教育会が小学生向けに作成した本を採用、使用テキスト「諏訪の自然観察ハンドブック」1995年 諏訪教育会 編纂発行。抜粋は、「第5章 諏訪にはどんな動物がどのような生活をしているでしょうか」
10月18日 森林文化見学会 参加者募集
今年度の森林文化見学会は、諏訪湖の水質保全のため無くてはならない諏訪湖流域 下水道 豊田終末処理場の見学会を実施します。