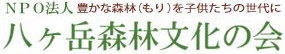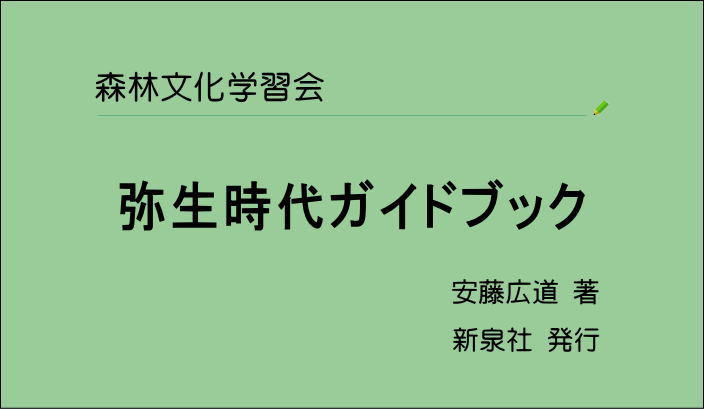R07年度学習会 ~八ヶ岳山麓で最盛期を迎えた縄文文化を知ろう~ [森林観察学習部会]
2025.11.6 11.20
後半10月からは、縄文文化に続いて、弥生文化について学習します。
<今年度の使用テキスト>
「弥生時代ガイドブック」安藤広道著 新泉社 発行
11月の学習
〇11月6日 ゆいわーく茅野 301会議室
3.縄文文化から弥生文化への変容………吉江
4.弥生文化・弥生時代の枠組み
5.弥生文化の農耕技術
〇11月20日 ゆいわーく茅野 101会議室
6.弥生文化の食料事情……………………井村e
7.日常生活の道具
8.弥生文化の集落
12月の学習予定
〇12月4日 ゆいわーく茅野 101会議室
9.人びとのすがたと人口………………吉田
10.集落間 地域間の関係の進展………吉田
11.祭祀、儀礼の発達……………………中野
〇12月18日 ゆいわーく茅野 101会議室
12.集団間の争い…………………………池田
13.墓からわかること……………………池田
14.弥生文化の世界観を探る……………渡邊
![]()
弥生時代ガイドブック 森林観察学習部会 井村悦子さんの資料より
6.弥生文化の食料事情
弥生文化の主要な農耕技術は水田稲作だった。
〇関西以西の多くの地域では、弥生文化の始まりからしばらくすると、人口が顕著に増加した。
→人口増加に伴い、生産性の高い水田稲作中心の生活になる。
登呂遺跡では、住宅跡数と水田跡面積から年間の熱量の半分程度をコメが賄っていたという研究結果もある。
〇人口増加がみられる地域の周辺では、早くから生産物を交換する分業的関係が発達した。
〇弥生文化の始まったころ、水田可耕地が少ない地域はコメへの依存度は低かった。
〇後期、終末期には、集落間、地域間の食料の動きが活発、複雑になっていく。
7.日常生活の道具
〇土器
<甕形土器>煮沸調理用土器
縄文文化では10リットル以上が目立つ。木の実のあく抜き等の前処理が必要だったためと思われる。
弥生文化で小型化したのは1回1回の炊事道具になったためで、装飾のない実用的になる傾向がみられる。
<壺形土器>貯蔵用土器
壺形土器は飾りがつくものが多く、コメの貯蔵や種籾の保管が特別の意味を持つようになったためだろう。
土器は。装飾の少ない朝鮮半島無文土器系、装飾が多い縄文土器系、双方の影響を受けている。
〇その他
縄文文化系技術、無文土器文化※2系技術、双方の影響を受けている。
・刃をもつ石器(石製利器※)は、縄文文化、無文土器文化双方の技術系統がみられる。
・打製石器、一部の磨製石器 縄文文化系
・太形蛤刃石斧、扁平片刃石器などの磨製石器類と石包丁は無文土器系
・漁撈具や狩猟具、各種木製品、植物素材の容器や道具 は縄文文化系
※利器:鋭くとがった刃物、便利な道具
※2無文土器文化:朝鮮半島の青銅器時代に現れた土器文化であり、日本の弥生文化とも深い関係が深い。
〇木材の利用
水田や堰・水路の構築、住居各種施設の築造のための道具、農作業用農具、機織具(大陸系の技術)の材料に多量の木材が利用された。→木材加工技術も発達 彫刻手法を用いた容器もつくられるようになる。
8.弥生文化の集落
弥生文化始まりのころ、
・九州北部では無文土器文化系の竪穴住居、掘立柱建物、集落を囲む溝(環濠)からなる集落がつくられる。
→形を変えながら東海西部まで定着 縄文系の要素と混じりながら多様な集落を形成していく。
・関東・中部・北陸の集落は徐々に東海西部以西と類似した様相をみせてくる。
・東日本では晩期縄文文化と大きく変わらない集落が続き、人口の急増や大規模集落の形成は長く見られない。
<集落の立地の傾向>
・水田可耕地に集落が集中する傾向がみられる。
・水田可耕地がほとんどない場所に、狩猟や漁撈のためと思われる集落ができる。
・流通量が増えるに従い交通の要衝に集落がつくられる。
<集落内遺構>
・竪穴住居が圧倒的に多い。
・貯蔵穴や高床式倉庫も比較的よく発見される。
・貯蔵施設が纏まる区画、石器製作の場、広場や墓が居住域内に存在することもある。
・東海西部以西の大規模集落では、大型掘立柱建物などが集中する箇所、青銅製品、ガラス製品、鉄製品などの製作所が発見されることもある、
→社会が複雑化し分業が進む中で集落が複数の機能空間に分割されていった。
・人口が増加していた時期・地域では、集落を囲む環濠の発達も特徴的。
・西日本中心に高地性集落も多く発見される。
→環濠、高地性集落の形成は、集落のまとまり同士の軋轢が生じていたことを物語っている。
(更新日 : 2025年11月27日)