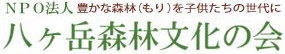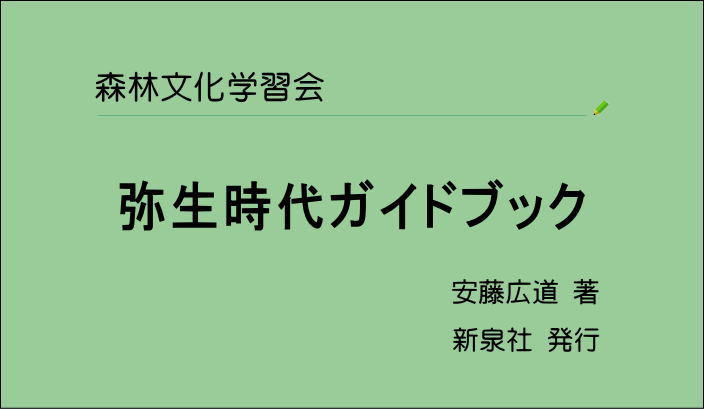R07年度学習会 ~八ヶ岳山麓で最盛期を迎えた縄文文化を知ろう~ [森林観察学習部会]
2025.10.23
後半10月からは、縄文文化に続いて、弥生文化について学習します。
<今年度の使用テキスト>
「弥生時代ガイドブック」安藤広道著 新泉社 発行
10月の学習
10月の学習項目は以下の通りでした。
10月23日
1.弥生文化とは?弥生時代とは?………井村j
2.弥生文化をどのようにとらえるのか
11月の学習予定
〇11月6日 ゆいわーく茅野 303会議室
3.縄文文化から弥生文化への変容………吉江
4.弥生文化・弥生時代の枠組み
5.弥生文化の農耕技術
〇11月20日 ゆいわーく茅野 101会議室
6.弥生文化の食料事情…………………井村e
7.日常生活の道具
8.弥生文化の集落
![]()
弥生時代ガイドブック 森林観察学習部会 井村淳一さんの資料より
1.弥生文化とは? 弥生時代とは?
文化人類学での「文化」
文化の定義/文化概念の検討:エドワード・タイラー:定義とその受容 参照
考古学的な文化
遺物における外観・形態等の異同によって確認される各種の様式は、相互に組み合わされて、一定地域に分布することが多い。そのうちの主要な様式を構成する型式の組列を上層・下層の双方にたどっていき、その連鎖が断絶するところを基準にすれば、時間的に重層する様式を一つの有意なまとまりとしてとらえることが可能となる。こうした様式もしくは型式の組列の時間的・地域的なまとまりの単位が考古学における文化である。
2.弥生文化をどのようにとらえるのか
弥生式土器の文化・時代を弥生(式)文化・弥生(式)時代と呼ぶようになった。これは1884年、東京都文京区本郷弥生町で一つの壺形土器が発見され、この土器が既に知られていた貝塚土器(縄文土器)や古墳出土の土器と異なることに注目した東京帝国大学人類学教室の面々が発見された土器に似た特徴を持つ土器群を発見地にちなんで弥生式土器と呼び始め、弥生式土器の文化・時代を弥生(式)文化・弥生(式)時代ということになったのが、「弥生」の始まり。(現在は、弥生式土器の文化・時代を弥生文化・時代と考える研究者はいない)。
弥生時代の定義:
1975年当時奈良国立文化財研究所所長(佐原 真さん)は以下を提唱した。
「日本で食料生産を基礎とする生活が開始された時代」で「前方後円墳の出現を持って古墳時代へと移行した」
山内 清男さん(日本の考古学研究の基礎を築いた研究者)はこれを踏まえて
狩猟・漁撈・採集生活を営んでいた人々による、時空間に連続しながら大陸との関係が希薄な土器型式のまとまりを縄文土器とし、その範囲を縄文文化と呼んだ。そして、縄紋文化の人々が大陸と関係をもって農耕をおこなうようになり、暮らしぶりが変容した段階の土器型式の時間的まとまりを弥生式土器、その範囲を弥生式文化とした。
(更新日 : 2025年10月30日)