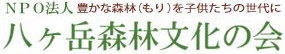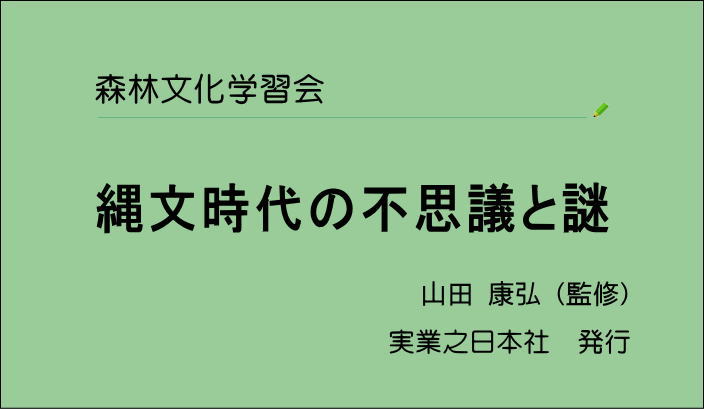R07年度学習会 ~八ヶ岳山麓で最盛期を迎えた縄文文化を知ろう~ [森林観察学習部会]
2025.9.4 9.18
5月1日から、今年度の学習会を開始しました。
今年のテーマは、今まで取り上げてこなかった縄文文化としました。
<今年度の使用テキスト>
「縄文時代の不思議と謎」山田康弘監修
実業之日本社 発行
今シリーズは、担当の負担を軽くするために、資料を作らず読み合わせをして、みんなで議論することにしましたので、内容の報告は、その回での話題1つを抜粋して掲載することにします。
9月の学習
〇9月4日
パート4
4~9 金色に輝く妊婦の土偶 国宝・縄文のビーナス…………………………池田
10~13 そのポーズ、どんな意味? フシギな土偶たち……………………中野
〇9月18日
パート4
14~16 なぜ人は縄文にひかれるのか?………………………………………井村j
10月の学習予定
〇10月23日
後半については、縄文に続いて弥生時代も少し知っておきたいと思うので、以下をテキストにして進めたいと思います。
使用テキスト ビジュアル版
「弥生時代 ハンドブック」安藤広道著 新泉社
![]()
縄文時代の不思議と謎
パート4 知っておきたい 縄文土器・土偶の秘密
森林観察学習部会 井村淳一さんの資料より
何が縄文にひかれるのか?
大ブームを生んだ縄文の謎と魅力
縄文にハマる理由:
〇縄文土器の造形や素朴な意匠を考古学的に捉える人、
〇アートと捉える人、
〇ユーモラスな土偶をマスコット的に捉える人
〇縄文時代の生活スタイルにスローライフやエコを感じる人
〇当時のスピリチュアルな暮らしの方が精神的に豊かだったと考える人
縄文ブーム:
縄文土器は近年になって価値を認められ、注目度が高まった。(国宝指定は平成に入ってから)
海外での縄文展での日本独特の文化が高く評価され、その逆輸入の効果。
しかし、遺跡保護・活用等の埋蔵文化財保護の動きは鈍い。
土偶の知名度上昇に一役買った映画
「ドラえもん 新・のび太の日本誕生」
この映画は1989年に公開された「ドラえもん のび太の日本誕生」のリメイク版で、この新旧映画の29年間の間に発見された新しい土偶等の研究成果が反映された。旧作公開時に小学生だった子供達が親になりその子供達が新作映画を観る年ごろになったことで親子そろって楽しめる映画になったことが大きい。
縄文土器の美術的価値に気づき
太陽の塔を作った岡本太郎
参考:「縄文土器論 四次元との対話」1952年 岡本太郎 発表
「縄文土器論」は、次のような文章で始まる。
縄文土器の荒々しい、不協和な形態、紋様に心構えなしにふれると、誰でもがドキッとする。なかんずく爛熱した中期の土器の凄まじさは言語に絶するのである。
激しく追いかぶさり重なり合って、隆起し、下降し、旋廻する隆線紋。これでもかこれでもかと執拗に迫る緊張感。しかも純粋に透った神経の鋭さ。常々芸術の本質として超自然的激超を主張する私でさえ、思わず叫びたくなる凄みである。
この論考の内容に興味にある方は、「縄文土器論 四次元との対話」でネット検索してご覧ください。
注:隆線紋:指や手のひら、足の裏の皮膚に現れる線状の隆起を指します。隆線文:縄文土器等の装飾として、細かい粘土紐を貼り付けて作られた線状の文様を指します
(更新日 : 2025年09月27日)