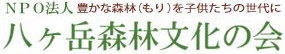~樹木医と市民の森の樹木巡り~
[森林観察学習部会]
2025.6.18
今年の秋の観察会は、これからの森づくりの基礎となるよう樹木の知識を広げるために、早くから講師探しをして、樹木医の根萩達也さんを探し当てました。
根萩さんは長く、長野県烏川渓谷緑地環境管理事務所に勤務され、一般公開している烏川渓谷緑地の管理をされていました。2005年、当会が「市民の森」に関する提言を茅野市に提出した年に、一般公開の森の参考にと視察に行ったのが烏川渓谷緑地で、根萩さんにガイドして頂いています。
引き受けるかどうか、現地を見てからと言うことで、今回、市民の森を案内しました。
この日はスタッフの役得で、講師を一人占め。沢山の情報を頂きました。話のほんの一部を紹介します。
〇食痕がある落葉をみて、モモンガかムササビがいる。
〇山頂コース中腹のホオノキの大木
上の枝がVの字に2本出ている。Vの字の部分で両枝の鬩ぎあいがあり、ここから弱ることがある。
〇傾斜地での広葉樹と針葉樹の根の張り方が違う。
広葉樹は崖の上側から引っ張りあげ(引張りあて)、針葉樹は崖の下側から圧縮する(圧縮あて)ことで木本体を支えている。
だから、広葉樹は崖の上側の根が、針葉樹は崖の下側の根が大事。歩道を作るときは、それを意識する。
南コースの脇の崖で手前の根が露出している木(コナラ)があるが、もし、針葉樹なら即危ないが、広葉樹だから暫くはもつ。土の浸食がすすむと危ない。
〇伐倒の巻添えで傷がついた樹皮は、土に近い所だと致命的。土から雨で跳ね上がる雑菌で腐りやすい。
〇同じ蔓植物でも、木を締め付けて成長を阻害するものがある。観察のために残すか、木のために切るか悩ましいところ。
〇樹木は春、葉が出るまでが一番弱い。
樹木は夏秋に光合成で栄養を貯めて冬を越し、春先、その栄養を使って葉を出し、花を咲かせる。
葉が光合成を始めればその栄養が使えるが、それまでは冬の貯えで過ごさなければならない。
〇南コースのナツハゼの隣のサクラの根元に昨年もあった樹液(黄色のドロドロ)は、原因を調べると持ち帰られた。
質問には丁寧な説明が頂けるので、皆さん、秋の観察会(10月5日)に、是非参加しましょう!!
(更新日 : 2025年06月28日)