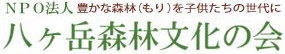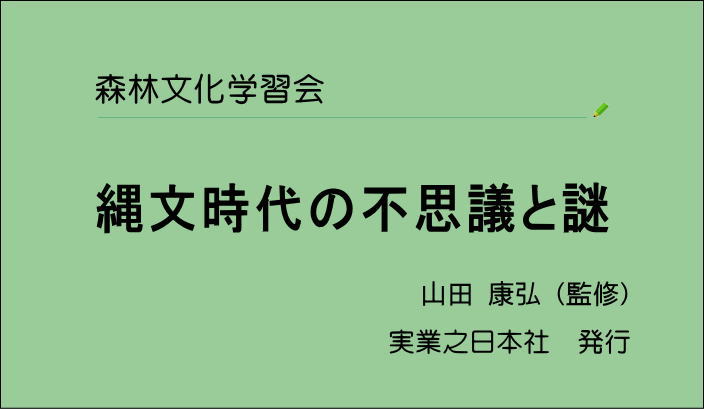R07年度学習会 ~八ヶ岳山麓で最盛期を迎えた縄文文化を知ろう~ [森林観察学習部会]
2025.6.5 6.19
5月1日から、今年度の学習会を開始しました。
今年のテーマは、今まで取り上げてこなかった縄文文化としました。
<今年度の使用テキスト>
「縄文時代の不思議と謎」山田康弘監修
実業之日本社 発行
今シリーズは、担当の負担を軽くするために、資料を作らず読み合わせをして、みんなで議論することにしましたので、内容の報告は、その回での話題1つを抜粋して掲載することにします。
6月の学習項目は以下の通りでした。
〇6月5日
パート1 意外と知らない!縄文時代の素朴なギモン11
9~11 縄文人の数の概念など………南波
パート2 意外と楽しく暮らしていた! 縄文人の衣食住
1~3 老若男女の役割分担は?など…矢崎
〇6月19日
パート2 意外と楽しく暮らしていた! 縄文人の衣食住
4~7 洗練されていた保存の知恵……井村
8~12 機能的だった縄文漁具………吉田
7月の学習予定
〇7月3日
パート2 意外と楽しく暮らしていた! 縄文人の衣食住
13~16 縄文アクセサリー…………渡邊
17~20 縄文人の酒造り……………野崎
〇7月17日
パート3 どこで何が起こっていた?縄文日本の風土と出来事
1~4 縄文時代の津波の痕跡…………井村j
5~7 全国縄文遺跡マップ……………池田
![]()
縄文時代の不思議と謎
パート1 意外と知らない!縄文時代の素朴なギモン11 森林観察学習部会 南波一郎さんの資料より
素朴な疑問9 階層が存在し、病人は介護されていた! 高度な縄文社会
1.縄文時代のイメージが近年の研究で変わりつつある。
階層の無い平等な社会→ 一部では階層が存在する高度に組織化された社会
背景:2棟~3棟の小規模な集落イメージが三内丸山遺跡(青森県、1992年発掘開始、日本最大規模の縄文遺跡)の発見、調査により縄文時代の概念が変化している。
2.三内丸山遺跡のすごさ
①大型竪穴住居を含む780件におよぶ住居跡、広さ42ヘクタール
➁祭祈用建物、共同ごみ捨て場、貯蔵穴、調理施設、埋葬施設
③1700年継続、多様な遺物
④2021年に世界文化遺産に登録
3.これだけの大規模な集落維持には指導者(年長者?)が必要になり階層が出来る。
それは発見された墓の格差からも想像される。
集団生活ゆえの暴力沙汰もあったが共同体意識からの弱者保護(介護)もあったと遺体の痕跡から想像される。
素朴な疑問10 足し算も引き算も割り算もしていた!? 縄文人の数の概念
1.縄文時代には既に数の概念及び足し算等の概念はあった→秋田県の大湯環状列石から出土した土版がその証拠
2. 3と5と7を特別視していた→3本指の土偶や突起が5つある土器が多く発見された。
3. 35cmが長さの基準だったのではないか
→遺跡の構造物で柱間の距離が35cmの倍数になっている。「縄文尺」とも言われ、人間の肘から手首までの長さに相当し身体尺と言われる。
素朴な疑問11 遺跡から出土した土器や土偶は、どうやって復元しているのか?
1.地元の埋蔵文化センターで洗浄、乾燥させる。破損部分は仮組し接着剤で修復される。
2.「遺失物発見」として警察に届け、同時に「埋蔵文化財発見届」を地元の教育委員会に提出し文化 財として認定される。
3.特別に重要な資料はさらに専門の修復師による復元作業が行われる。
(更新日 : 2025年06月28日)